金券ショップ J・マーケット チケットマスター
クオカードが株主優待で人気の理由とは?銘柄を選ぶポイントも紹介
投資初心者に人気の株主優待品の一つにクオカードがあります。クオカードは全国で幅広く使えるプリペイド式の商品券で、贈答品や景品としてもおなじみです。株主優待として企業がクオカードの提供を発表すると、株価が急騰するケースもあるほど注目度の高い優待品です。
この記事では、クオカードが株主優待で支持される理由や、クオカード優待銘柄を選ぶ際のポイント、実際の使い方や注意点を詳しく解説します。
目次
クオカードは株主優待として人気
クオカードは株主優待品として高い人気を誇ります。その理由は、現金に近い使い勝手と、誰にとっても嬉しい汎用性があるからです。
クオカードはコンビニや書店、ガソリンスタンド、ドラッグストア、飲食店、ホテルなど全国約6万もの加盟店で利用でき、実質的に「お買い物券」として活用できます。さらに、有効期限がないため焦って使う必要もありません。
配当金と異なり、受け取った額面そのままを買い物に充てられる点も魅力で、税金面でお得になる場合もあります。
このように、どんな株主にも使いやすく価値を実感しやすい優待品であることが、クオカードが人気の理由です。
クオカードが株主優待に人気の理由

クオカードが株主優待として選ばれる主な理由を詳しく見ていきましょう。
すぐ使える
クオカードは受け取ってすぐに日常の買い物に使える点が大きな魅力です。
例えば、500円や1,000円分のクオカードなら、コンビニでおにぎりやドリンクを買ったり、ドラッグストアで日用品を買ったりと、使い道に困りません。現金同様に1円単位で利用できるうえ、買い物のたびに残高が差し引かれるプリペイドカード方式のため、端数も無駄になりません。
配当金で1,000円をもらっても税金が引かれてしまいますが、クオカードなら額面どおりの金額をそのまま買い物に充当できるのも嬉しいポイントです。
使える店舗が多い
クオカードは使える店舗の多さが群を抜いています。
コンビニ大手のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートをはじめ、ポプラやデイリーヤマザキといったコンビニでも利用可能です。
さらに、書店(紀伊國屋書店や有隣堂など)やドラッグストア(マツモトキヨシ等)、ファミリーレストラン(デニーズ等)、カフェ(上島珈琲店等)、ガソリンスタンド(ENEOSやJA-SS)など、様々な業種で使えます。
その加盟店舗数は全国で約6万店にものぼり、地域を問わず利用できるため、株主の居住地やライフスタイルに左右されない優待品といえるでしょう。どこでも使える安心感が、クオカード優待の人気を支えています。
有効期限がない
クオカードには有効期限が設定されていません。そのため、受け取ったクオカードを「期限内に使わなきゃ」と慌てる必要がなく、自分のペースでゆっくり使えます。
自社製品の優待券やクーポン券だと有効期限や利用条件がある場合も多く、気づいたら期限が切れていた…といったことも起こり得ます。一方、クオカードであればいつでも好きなタイミングで使えるため、優待を無駄にしにくいのです。
半年前にもらったクオカードを今になって使う、といったことも可能で、忙しい人や忘れっぽい人にも優しい仕様です。
企業オリジナルデザインは記念になる
クオカードは企業ごとにオリジナルデザインが用意されることが多く、株主にとっては記念品としての価値も楽しめます。企業ロゴやキャラクター、風景写真などが印刷された限定デザインのクオカードは、その企業の株主である証ともいえ、コレクションしている投資家もいるほどです。
アニメキャラクターや創立◯周年記念デザインのクオカードが送られてくることもあり、デザイン目当てで株を保有するファンも存在します。優待として受け取ったクオカードを使わずにとっておく人もいるくらい、思い出に残る一枚になるのです。
単なる金券以上に、株主と企業のつながりを感じられるアイテムとしても人気を集めています。
税金がかからないケースがある
クオカード優待には税制面で有利なケースがあります。通常、株式の配当金には約20%の税金が源泉徴収されますが、クオカードの優待の場合、額面そのままを受け取って使えるため一見「非課税」に思えます。厳密には株主優待でもらった金券類は雑所得となり、年20万円を超えれば確定申告が必要です。
しかし、会社員など給与所得者の場合、優待金券類の年間合計額が20万円以下なら所得税の申告不要とされています。(住民税は別途申告義務あり)
多くの個人投資家にとって、優待で受け取るクオカードの額が年20万円を超えることは稀でしょう。そのため、配当金で受け取るよりクオカード優待として受け取った方が、実質的に手取りが増える可能性があるのです。
株の保有年数で金額が変わる
クオカード優待では、長期保有するほど額面金額がアップするユニークな制度を採用する企業も多く見られます。
稲畑産業は保有期間6か月未満で500円分、6か月以上で1,000円分、3年以上で2,000円分のクオカードがもらえる仕組みです。同様に、10年以上の長期保有で優待額が大幅にアップする企業もあります。(例:プロネクサスは1年未満500円→10年以上3,000円)
このように「持ち続けるほどお得」な設定があると、株主も長期投資のインセンティブが高まり、企業側にとっても安定株主の確保につながります。投資初心者にとっても、長期保有の魅力を体感できる仕組みといえるでしょう。
クオカードの優待を選ぶ際のポイント

クオカード優待を提供する企業は数多く存在しますが、銘柄選びではいくつか注意したいポイントがあります。
せっかく魅力的な優待でも、企業の業績悪化で急に廃止されてしまっては有効活用ができません。また、どうせなら配当金も優待も両方もらえる企業を選ぶ方が投資効率も高まります。
以下では、クオカード優待銘柄選定時に押さえておきたいポイントを解説します。
業績が赤字の可能性がある銘柄は避ける
クオカード優待の銘柄を選ぶ際は、企業の経営状態に注意しましょう。
業績が悪化し赤字に転落するような企業では、配当金カットや株主優待の廃止・改悪が行われるリスクがあります。実際、株主優待は企業の任意の施策であり、経営環境の変化や方針転換によって突然廃止される例もあります。
特に、利益が出ていない状態で株主優待を続けるのは難しいため、継続的に黒字を維持している企業を選ぶことが重要です。財務諸表で利益や自己資本の状況確認、過去のIRニュースで優待方針の継続性を探ると良いでしょう。
安定経営の企業であれば、優待廃止のリスクも低く、万一廃止となっても配当で還元される可能性があります。赤字リスクの低い健全経営の企業に注目しましょう。
クオカード優待の実績がある銘柄
クオカード優待の実績が豊富な企業を選ぶのもポイントです。毎年安定してクオカード優待を実施している銘柄や、長期にわたり優待内容を維持・拡充してきた企業が挙げられます。
リコーリースは連続増配で知られる優良企業で、株主優待としてクオカードを長年提供し続けています。
日本取引所グループも倒産リスクが極めて低い安定企業で、継続保有期間に応じクオカード額面が増える優待を実施。
他にも、毎年クオカード優待ランキングの常連となっているTBKやINPEXなど、投資家に人気の銘柄があります。
過去の実績を踏まえて、優待方針がぶれにくい会社を選ぶと、安心してクオカード優待を享受できるでしょう。
クオカード優待と配当の両方を受け取れる銘柄を選ぶ
株式投資のリターンは株主優待だけでなく配当金からも得られます。そこで、クオカード優待と配当金の両方を出している銘柄を選ぶと、総合利回りが向上するためおすすめです。
クオカードは額面そのまま使える強みがありますが、配当金と組み合わせれば一層お得です。年1,000円分のクオカードに加え1株あたり50円の配当を出す企業なら、株主は優待と配当でダブルの利益を享受できます。
企業側にとっても、優待品をクオカードにすると自社製品送付より配送料を抑えられるメリットがあり、配当も出せる財務体力を持っていると判断できるでしょう。配当+優待の合計利回りが高い銘柄は市場でも注目されやすく、結果として株価上昇も期待できます。
優待と配当のいいとこ取りができる銘柄を探してみましょう。
クオカードを使用する際に押さえておきたい注意点

クオカードは使い勝手が良い半面、利用上の注意点もあります。せっかくの優待を無駄なく使うために、残高の確認方法や支払い時のルールを知っておきましょう。
また、クオカード自体の取り扱いについても、誤解しがちな点があります。以下に、クオカード使用時に押さえておきたいポイントを整理しました。
残高はレシートで確認
クオカードの残高確認はとても簡単です。加盟店のレジでクオカードを使って支払いをすると、支払後の残高がレシートに印字されます。
例えば、1,000円分のクオカードで300円の買い物をした場合、レシートに「残高700円」と表示される仕組みです。
また、クオカードの左下にある数字(0・5・10など)と穴の開いた位置でも大まかな残高を確認できます。次に使う時に残高不足にならないよう、レシートでこまめに残額をチェックすると安心です。
残高が足りない場合は差額を現金や他の支払い方法で併用できるため、1枚のカードを最後の1円まで使い切れます。
おつりは出ない
クオカードで支払う際は、おつり(現金のお釣り)が出ないことに注意しましょう。
クオカードはプリペイドカードのため、利用金額がカード額面以下でも現金の釣銭は受け取れません。1,000円分のクオカードで300円の商品を買った場合、残りの700円はカード内残高として記録されるだけで、お釣りとして現金ではもらえません。
ただし、カード内に残った金額は次回以降の買い物で引き続き使えます。もし購入額がカード残高を超えた場合も、不足分を現金などで支払えば併用可能です。
クオカードには残高があれば何度でも繰り返し使えるメリットがある反面、現金化はできない点を覚えておき、額面以上の買い物時に上手に使い切るようにしましょう。
転売や換金は禁止
クオカードは第三者への転売や現金への換金が禁止されています。公式サイトにも「換金・転売は禁止」と明記されており、金券ショップなどで買い取ってもらう行為も推奨されません。
そのため、ネットオークションなどでの転売は規約違反となります。さらに、企業からの株主優待品として受け取ったクオカードを換金目的で手放すことは、企業側の意図(株主への感謝)にも反する行為です。
株主優待としてもらったクオカードは、素直に自分や家族の生活に役立てるのがおすすめです。どうしても使い道がない場合でも、誰かにあげる程度に留め、現金化は避けましょう。
クオカードで購入できるもの・サービス
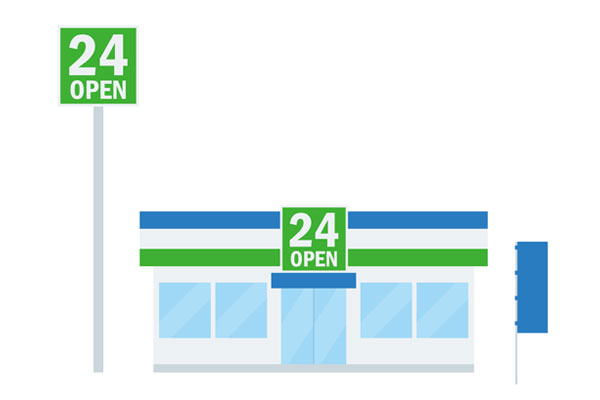
クオカードは幅広い品物・サービスの購入に使えます。日常の必需品から娯楽までカバーしており、株主優待として届いたクオカードを何に使おうかと考えるのも楽しみの一つです。
以下では、クオカードで購入できる代表的なものやサービスをカテゴリ別に紹介します。自分の趣味嗜好や生活スタイルに合わせて、上手に活用しましょう。
食品・日用品・医薬品など
クオカードは食品や日用品、医薬品の購入に活用できます。コンビニでお弁当や飲み物、お菓子などを買うのはもちろん、ドラッグストアでシャンプーや洗剤、風邪薬などの購入も可能です。
マツモトキヨシなどのクオカード加盟ドラッグストアでは、コンビニより安く日用品や第2類医薬品を買えることもあります。ただし、ドラッグストアでクオカード支払いした商品は返品不可の場合があるため注意しましょう。
日々の暮らしに必要な消耗品や食料品をクオカードで購入すれば、家計の節約にも役立ちます。株主優待でもらったクオカードをうまく使って、日常の支出を少しでも軽減できると一石二鳥です。
書籍・DVDなど
クオカードは本やDVD、CDなどの購入にも使えます。全国各地の書店がクオカード加盟店となっており、紀伊國屋書店、有隣堂、ジュンク堂書店といった大型書店から、地元の小さな本屋さんまで幅広く利用できます。
新刊小説やビジネス書、雑誌などを買う際にクオカードで支払えば現金不要で便利です。また、HMVの店舗ではCDアルバムや映画のDVDをクオカードで購入可能で、趣味の娯楽にも役立ちます。
株主優待のクオカードで自己投資として専門書を買ったり、リフレッシュのための映画DVDを買ったりと、教養や娯楽の充実に使うのも良いでしょう。金券ならではの柔軟な使い道で、楽しみの幅が広がります。
食事やコーヒーなど
クオカードは飲食店やカフェでも利用できます。
UCCグループが運営する「上島珈琲店」や「UCCカフェプラザ」などのカフェチェーンでは、クオカードでコーヒー代を支払うことが可能です。セルフ式のカフェからテーブルサービスの喫茶店まで加盟店があるため、買い物途中の休憩にも活用できます。
また、ファミリーレストランの「デニーズ」や静岡発の中華料理チェーン「五味八珍」などでもクオカード払いが可能です。家族で外食する際に優待のクオカードを使えば食事代の節約になり、お財布に優しいといえます。
さらにコンビニでお弁当を買って公園ランチ、といった使い方もできます。食事やカフェタイムにもクオカードを賢く使って、日々のちょっとした贅沢を楽しみましょう。
ガソリンスタンド
クオカードはガソリンスタンドでも使えます。
大手のENEOS(エネオス)の一部店舗やJA-SS(農協系スタンド)の給油所では、給油や洗車の支払いにクオカードを利用できます。セルフスタンドなら支払い機でプリペイドカードとして扱い、フルサービス店ならスタッフに手渡せばOKです。
また、ENEOSやJA-SSではそれぞれオリジナルデザインのクオカードを販売しており、もちろん通常の加盟店でも使用可能です。
ドライブや通勤でガソリン代がかさむ方にとって、株主優待のクオカードで燃料費を補えるのは嬉しいポイントでしょう。毎日の通勤、週末のレジャーなどの移動コストの節約にも役立つため、生活インフラへの支払いにもクオカードを活用してみてください。
ホテル
クオカードはごく一部ですがホテルの宿泊料金にも利用できます。
東京ディズニーリゾートのオフィシャルホテルである「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」や「東京ベイ舞浜ホテル」では、宿泊費や館内レストラン・ショップでの支払いにクオカードが使えます。また、青森県の「龍飛崎温泉 ホテル竜飛」でもクオカードおよび電子版のQUOカードPayが利用可能です。
これらは加盟店の中でも数少ないホテル利用の例ですが、旅行や出張時に株主優待のクオカードを活用できるのは魅力的です。高額な宿泊費の一部をカバーできれば経済的な助けになりますし、優待を活用して普段より少し贅沢なホテルに泊まってみるのも良いでしょう。
使えるホテルは限定的のため、事前に加盟店か確認してから利用してください。
購入できないもの・サービス
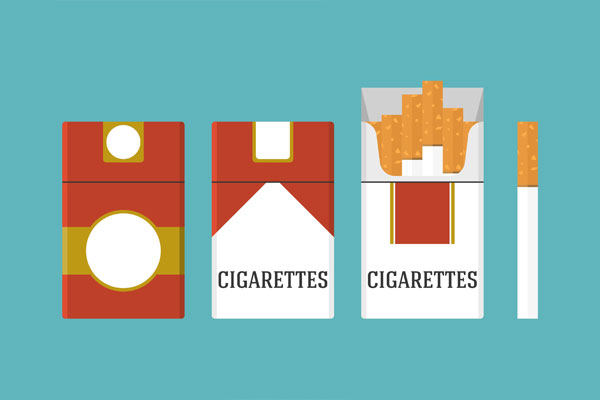
ほとんどの物が買えるクオカードですが、一部購入できない商品やサービスも存在します。加盟店でも特定の商品はクオカード払い不可のケースがあるため注意が必要です。知らずにレジに持っていくと使えず恥ずかしい思いをするかもしれません。
以下に、クオカードで支払いができない代表的なものを紹介します。計画的に優待を活用するためにも、事前に確認しておきましょう。
たばこ
クオカードでは、たばこ(タバコ製品)の購入はできません。どの加盟コンビニでも共通のルールで、レジでクオカードを出してもタバコ代の支払いには充てられないためご注意ください。
理由としては、タバコは国が価格を厳格に管理しており、金券による購入が制限されているからです。喫煙される方は株主優待のクオカードでタバコを買えないのは残念に思うかもしれませんが、これは制度上の決まりです。
なお、電子タバコ関連製品やニコチンガム等についても扱いは各店舗の判断となるため確認する必要があります。基本的にはタバコ製品全般がクオカードの利用対象外と覚えておきましょう。
その他
タバコ以外にも、クオカードで購入できないものはいくつかあります。代表的なものは以下のとおりです。
- 郵便切手
- はがき
- 収入印紙
- プリペイドカード類
- 交通系ICカードのチャージ
- 各種チケット類(イベントチケットや興行券など)
- 公共料金等の支払い
さらに、コンビニごとに独自に定める除外商品もあります。例として、ファミリーマートではゴミ処理券やコピー・FAXサービス等に使えず、セブン-イレブンでも公共料金や電子マネーチャージなど一部サービスは対象外です。
金券や換金性の高いもの、料金支払い代行系はクオカードNGと覚えておきましょう。株主優待のクオカードを計画的に使うためにも、「これは使えないかも?」と思ったら事前に店舗で確認すると安心です。
まとめ
①株主優待としてのクオカードは、現金同様に幅広い店舗で使えて有効期限がないことから初心者にも人気が高い優待品
②クオカード優待を選ぶ際は、税金が源泉徴収されない点で配当金より有利なケースがあることや、長期保有により優待額が増える仕組みを導入している企業が多い
③クオカードの銘柄選定は安定した経営状態(継続的な黒字や増配の実績など)や配当との組み合わせで総合利回りが高い企業を重視する
④クオカードの具体的な使い方や注意点は、残高はレシートで確認できる、1円単位で使い切れるが現金化は不可
⑤購入できないもの(タバコ・切手・印紙・収納代行など)や、ホテルでの利用は一部店舗のみなどの制限事項もあるため、優待を上手に活用するためには事前確認が大切
※本記事は公開時点の情報になります。
記事内容について現在の情報と異なる可能性がございます。
